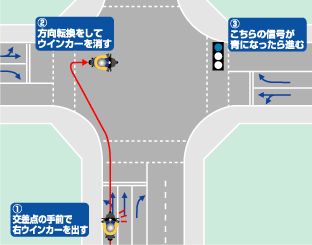
▲図.1 二段階右折概要[4]
公開日:2006-04-08
更新日:2012-12-14
二段階右折とは、原動機付き自転車(以下原付)と軽車輌[1]に課される右折方法の一つです。日本では道路交通法(以下法)34条3項及び5項に規定されています。
二段階右折は、進行車道の左端から一旦交叉点を直進し、渡った先で方向を右に変え、右折先の信号が青になってから直進します(図.1)[2] これに対し、進行車道の右側から直接交叉点を曲がる通常の右折を小回り右折といいます。
この規定の趣旨および意義は公開されていません。恐らく、それまで左端を走っていた軽車輌が、低速のまま道路の右側まで一気に車線変更するのは危険であるためと筆者は考えています[3]
他の条文との関係上、交叉点の直進先にて方向転換した時点で右折行為は完了したものと解釈されるようです。そのため、方向指示器は方向転換時に消灯し、以降は進行方向上の信号に従わなければなりません。
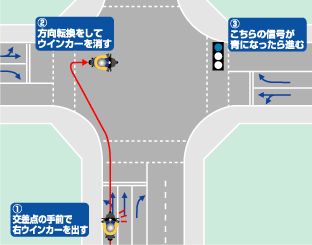
▲図.1 二段階右折概要[4]
[註.01] 荷車、馬車、自転車など
[註.02] 進行経路の形から「フックターン」(Hook Turn)と表現する国もある。
[註.03] ただしこの場合、転回に規制がかけられていない理由が説明出来ませんが。
[註.04] 日本自動車工業会より
法によると、軽車輌の場合は無条件で二段階右折しなければなりません[法34条3項]。一方原付の場合は、
においては二段階右折をし、それ以外の場合は小回り右折をしなければならない[法34条5項]とされています。
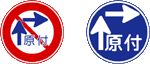
▲図.2 二段階右折に関する標識(左が禁止で右が指示)
- 第2項
- 自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。
- 第3項
- 軽事両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。
- 第4項
- (省略:要は道路が一方通行の時は右側によれという話)
- 第5項
- 原動機付自転車は、第2項及び前項の規定にかかわらず、道路標識等により交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことが指定されている道路及び道路の左側部分(一方通行となつている道路にあつては、道路)に車輌通行帯が3以上設けられているその他の道路(以下この項において「多通行帯道路」という。)において右折するとき(交通整理の行われている交差点において右折する場合に限る。)は、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。ただし、多通行帯道路において、交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことが道路標識等により指定されているときは、この限りでない。
しかし、この規定だけでははっきりしない点がいくつか考えられる。
二段階右折はあくまでも「右折」の方法です。従って、形としては交叉点を直進するものの、右折の合図(指示器等)を出さなければなりません。出さなければ合図制限違反、左折合図を出していると合図不履行に当たります。
二段階右折に関する条文上、二段階右折かどうかは今走っている道路の車線(車輌通行帯)数で決まります。そのため、小さな(2車線以下の)道路から大きな(3車線以上の)道路にはいるときは、二段階右折をしてはなりません[5]
[註.05] 但し標識で指示がある場合はそちらが優先される
元が2車線の道路においても、渋滞対策として交叉点手前のみ右左折専用車線を設けている場合があります。
法的に車輌通行帯とは、車輌が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。
[法2条1項7号]と定義されており、指定通行区分は問いません。また二段階右折かどうかは「交叉点にさしかかったときの車輌通行帯の数」で決まるため、たとえ直前で増えたとしても二段階右折をしなければならないと解釈されます。
従って、交通量が多く、かつ横幅に余裕がある道路では、二段階右折を課される可能性がかなり高いとみるべきです。
道路交通法施行令(以下施行令)55条別表1の備考2の40の2及び法35条では
「指定通行区分違反」とは、法第三十五条第一項の規定の違反となるような行為をいう。
車輌(軽車輌及び右折につき原動機付自転車が前条第5項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。)は、車輌通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、前条第1項、第2項及び第4項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車輌通行帯を通行しなければならない。ただし、第40条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。
と規定されており、原付や軽車輌の二段階右折時において、指定通行区分の制限は除外されています。従って左折専用車線を直進しなければなりません[6]
大きな交叉点を右折する車は、たとえ左折車線にいても原付が右折合図が出ている場合は直進するので注意してください。
[註.06] ところが、Web上ではこの例外を知らずに「最も左側の直進車線を走らなければならない」と言う意見が散見されます。それどころか取り締まる警察官が勘違いしている例も数件報告されているようです……。
施行令2条では、
車輌は、黄色の燈火又は赤色の燈火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること。この場合において、交差点において右折する多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車輌は、直進する軽車輌とみなす。
と規定されており、直進矢印の信号に従わなければなりません。右折や左折信号で直進すると信号無視に当たります。
しかし、左折専用車線で直進信号を待つという行為は、常識的に考えて極めて危険ではないでしょうか? 左折する車輌にとっても邪魔でしょうし……。もし「危ない」と感じれば、緊急避難の原則に基づいて直進車線に避難しても、恐らく違反に問われることはないと思います。
二段階右折について、丁字路(T字路)における特段の規定が見あたらないため、原則通り二段階右折すべきと考えられます。
経験上、大抵の丁字路は「二段階右折禁止」の標識が出ていますが、稀にバス停のような「二段階右折用のくぼみ」が設けられていたり、明らかに設置し忘れている丁字路も見掛けられる。そのような時は右折を諦めた方が安全と思われます。
なお、標識の登場が明らかに遅い場合、警察や国家公安委員会に訴えれば一応善処されるらしいです。
原則として、原付及び軽車輌以外の車輌の二段階右折は認められていません。従って排気量50cc以上の小型二輪(第二種原付)や普通・大型二輪が二段階右折を行うと交叉点右左折方法違反に当たります[7]
もしこれらの車輌で二段階右折する必要があるときは、エンジンを切って降車し、手押しで一旦歩道に入れば右折に当たりませんので、状況に応じて活用しましょう。
[註.07] 但し警察署によっては黙認する例もある模様(後述)
二段階右折の規定はあくまでも右折する際の規定であり、転回(Uターン)の際には適用されません。但し、大きな道路では転回が禁止されている事が多いため、注意が必要です。
安全のためとはいえ、原付の二段階右折に関してはかなり怪しい部分が見受けられます。そのくせこれが白バイの格好の餌食にされますので、一番の対策は、予め二段階右折しなくてもよい交叉点を把握するなど、通る道路をよく知っておく事しかないように思います。
もちろん、それは事故防止の観点からも非常に有効であるのは間違いないでしょうが、法の不備であるならば、早急に是正されるべきではないでしょうか。
本記事を公開した後、メールにて、世田谷警察・交通規制課によると、二段階右折は、原付一種以外でもやってよいとの事です。
という指摘を受けました。気になったのでさらに調べたのですが、やはり一種原付以外の二段階右折についての規定は何処にも見あたりませんでした。見あたらない以上、右折方法に関する原則に従うものと筆者は解釈しています。
しかし、調べてみて分かりましたが、この二段階右折については、警察側にもかなり解釈の「差」があるようです。本来いくら警察が「OKだ」と言っても法律的にNGならば、やはりそれはNGである[8]ことには違いありません。
……とはいえ、「許容」してくれるのなら、それはそれで構わないのではないでしょうか。別に、原付以外の二輪が二段階右折をしたからと言って、特別危険が生ずるとも考えられませんし。
ただ、もしそれで捕まってしまった時には、間違った情報を吹き込んだ警察の人を恨む以外にないですね[9]
筆者が住む兵庫県の場合、二段階右折が課される交叉点には、二段階右折する車輌が待機する専用の標識(白線)が定義されています。

▲撮影:兵庫県神戸市
これがあるおかげで、二段階右折をすべきなのかしてはいけないのかの区別が簡単につく上、二段階右折を忘れずに実行できるという利点があります。他の都道府県でも積極的に採用するべきではないでしょうか。
別の方からこの記事に対してこんなご質問を受けた。
失礼します。
突然ですが、以前二段階右折について書かれていたことがありますよね。
そのことについてなんですが、私は先日、指示器を右に出して通行していたところ、警察官の方に注意されました。
私も指示器は右だと思っていたので驚いて、ネットで調べていたところ、高天原[10]さんの文章に出会ったわけです。
そこで質問なんですが、高天原さんは二段階右折についての文章で多くの根拠条文をあげられていました。しかし、指示器を右に出さなければならないという記述については根拠条文があげられていませんでした。私も独自で調べましたが、該当する条文はありませんでした。
高天原さんは何を根拠に右だとおっしゃっておられたのでしょうか。
これからのためにはっきりさせたいのです。お時間があれば教えてください。
突然のメール、失礼しました。
これに対して筆者の返答は次の通り(若干編集している)
こんばんは、「久幸繙文」管理人の久樹輝幸です。
早速ご質問の件に入りますが、二段階右折の合図についての根拠法は、通行の右折と同じく、道路交通法第34条「左折又は右折」及び第53条「合図」と、道路交通法施行令第21条「合図の時期及び方法」にあると考えています。
2 自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。
5 原動機付自転車は、第二項及び前項の規定にかかわらず、道路標識等により交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことが指定されている道路及び道路の左側部分(一方通行となつている道路にあつては、道路)に車輌通行帯が三以上設けられているその他の道路(以下この項において「多通行帯道路」という。)において右折するとき(交通整理の行われている交差点において右折する場合に限る。)は、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。
車輌(自転車以外の軽車輌を除く。第三項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
2 前項の合図を行なう時期及び合図の方法について必要な事項は、政令で定める。
法第五十三条第一項 に規定する合図を行なう時期及び合図の方法は、次の表に掲げるとおりとする。
合図を行なう場合 合図を行う時期 合図の方法 右折し、又は転回するとき。 その行為をしようとする地点(交差点において右折する場合にあつては、当該交差点の手前の側端)から三十メートル手前の地点に達したとき。 右腕を車体の右側の外に出して水平にのばし、若しくは左腕を車体の左側の外に出してひじを垂直に上にまげること、又は右側の方向指示器を操作すること。 この場合、原動機付自転車は右折をするために合図を出さなければいけないわけで、しかも二段階右折は「右折」に関する規定ですから、右折の合図を出すのが正解だと判断いたしました(法34条5項には
交差点における原動機付自転車の右折につきと明記されています)また、指示器を右に出すという記事は、拙作の他にも、記事中で引用している日本自動車協会の記事や、交差点予知情報ホームページの記事などでも紹介されています。
以上の理由から、私は、警察の方が誤った認識を持っているのではないかと考えてます。
(※記事中追記に書きました通り、道交法に関しては警察の方でさえ、必ずしも正しい知識を持っているとは限らない状況です)
念のために大阪の交通関係の都道府県条例を大阪府例規集にて調べてみましたが、特に二段階右折について言及している箇所は見あたりませんでした。注意をされた警察官の方がどういう根拠を持っていたのか分らない以上、私の方から言えるのはこれぐらいになります。
あまり実のある答えにはなっていませんし、法律の専門家でもない素人意見ではありますが、ご参考になれば幸いです。
つまるところ、二段階右折の合図について特別の規定はないから、一般的な右折のやり方をすべきなのだろうというのが筆者の見解です。
[註.10] 旧サイト名
本記事はあくまでも筆者が法及び施行令を読んだ上での解釈であり、この通りにやって捕まったり事故にあったりしても、筆者は責任を負いかねます。自己責任かつ安全第一でお願いします。